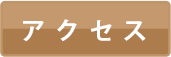特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」フリーランス新法について 【2023年事務所ニュース 夏号】
弁護士 笠置 裕亮
「新しい資本主義実現会議」の事務局を置く内閣官房が主導する形で、2022年9月、フリーランス新法の法案骨子が示され、パブリックコメントの手続に付されることとなった。ところが自民党内からは、法律として一律に規制をしていくことに対する異論が噴出し、2022年中における立法化は見送られた。
この挫折を踏まえ、2023年の通常国会に提出され、2023年4月28日の参議院本会議にて可決、成立したのが、今回の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(「フリーランス新法」)である。
フリーランス新法の特徴は、①下請法を参考に、発注者と受託者(フリーランス)との間の取引を適正化させる規制を定めていること、②労基法や職安法を参考に、フリーランスの就業環境を整備する趣旨の条項を定めていることにある。
これらは、発注者が事実上、仕事を丸投げていれば済んでいたこれまでの状況を大きく変えうるものであり、フリーランスの就労環境を大きく改善するきっかけとなるものであることは間違いない。
しかし、決定的に不十分な点がある。
最も大きな点が、契約内容明示義務が抜け落ちていることである。
新法3条1項では、発注時の条件明示義務を課され、新法12条では職安法を参考に募集時の募集条件明示義務が定められている。ところが、最も肝心な契約締結時の契約内容明示義務は、新法では何らの規定もないのである。そのため、例えば募集時には業務委託事業者Aが月額報酬30万円での募集を行ったにもかかわらず、契約時にそのとおりの契約書が作られず、仕入れなどの業務開始に必要な準備が整った段階になって初めて、月額報酬がなぜか20万円に減額されていたというようなトラブルが生じかねない。
契約締結時における契約内容明示義務を法的義務として定めなければ、契約書が作成され、フリーランスが法的保護を受けられる可能性は極めて低くなる。単発で業務を受注する場合には、特に弊害が大きい。
これについて、国会審議の中での指摘を踏まえ、参議院の付帯決議の中で、「業務委託に係る契約締結時における契約内容の明確化の必要性について、本委員会において参考人から出された意見も参考にしながら検討すること。」との条項が入った。実効性のある保護を実現するためには、可及的速やかに法改正が行われるべきである。
適用対象者となる者の定義が広すぎることも問題である。新法では、個人であって、従業員を使用しないもの、または、法人であって、代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないものということになったが、これでは他人の指揮命令下のもと労務提供を行っている労働者性を有する者も多く含まれてしまう。労働者性を有する者には新法ではなく労働法が適用されることは強調されなければならない。
下請法の劣化コピーになっている点も見過ごせない。新法5条は、下請法の規定を参考に発注者の禁止行為等を定めた規定であるが、下請法4条1項2号で定められた、報酬不払規制が入れられていないことである。そもそも下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」であり、この規定は下請法の規定の中の一丁目一番地といってもよい重要な規定でもあるが、新法は下請法4条をほぼコピーアンドペーストしつつも、これをあえて脱落させている。フリーランスが巻き込まれるトラブルの中で、典型的なものが対価の不払であるにもかかわらず、である。この点もまた、新法の改正時に速やかに見直されるべき規定である。
課題の多い法律ではあるが、ないよりはずっと良い法律ではある。この法律を活かすも殺すも、今後の活用・運用次第である。フリーランスの側の立場としては、新法に基づく申告を積極的に行い、今後の法律の見直しに際して意見を述べ、よりよい改正に結び付けていくべきである。